ORICON NEWS
芸能人の急速なClubhouse離れの背景 “クローズド”だからこそ、より資質が問われる場に
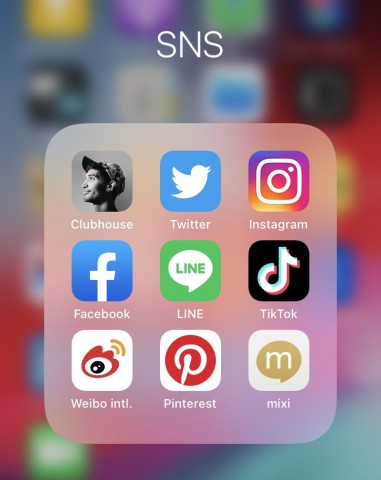
SNSアプリ
“閉鎖性”ゆえに、メディアでは見られない芸能人たちの雑談が展開
本国アメリカでは昨年の4月にサービスが開始されたが、日本では今年1月23日にβ版が運用開始。芸能界における先駆者は元AKB48の小嶋陽菜で、1月27日に自身のアパレルブランド「Herlipto」の採用について語るトークルームを作ると、一瞬にして視聴者は1200人超え。Twitterのフォロワーたちも「こじはるのクラブハウス聴きたかった」と騒ぎ出し、Clubhouseはトレンド入りしたのである。
すると、こじはるに続けとばかりエハラマサヒロ、EXIT・りんたろー。、ホリエモン、藤田ニコル等々、影響力のある著名人がInstagramやTwitterで登録を報告し、1月29日の時点ですでに日本のApp Storeの無料アプリランキングで1位になる…といった具合に急速に広まっていった。
芸能人や有名人がClubhouseに殺到したのは、もちろん話題作りだったり、新しいもの好きという側面もあるだろうが、やはりその閉鎖性と即時性ゆえだろう。録音やアーカイブを残すことが禁止されていることで、所属事務所を通すことなく、収録の合間や休憩時間などで気楽にトークルームを開設できる。たとえば小島瑠璃子が松尾豊教授にAIについていろいろ聞いてみたり、タレントが政治家と政治について語り合ったりと、普段のテレビやラジオ番組では見られない組み合わせや、オンタイムならではの雑談が展開されているのだ。
また、日本テレビの森圭介アナによるアナウンサー就活相談など、トークルームではイベントレベルのことまで実施されており、2月5日放送『アナザースカイII』(日本テレビ系)に出演した実業家・前田裕二氏のように、テレビ放送と同時にClubhouseで副音声を配信するなど、いわばテレビの「dボタン」のような使い方までされているのである。
即時性の高さゆえに、自身の商品価値を落としてしまう側面も
また、一般のリスナー側もそんな芸能人・有名人同士の雑談をタダで聴くことができるし、スピーカー(トークルームの主催者)が許可すれば、有名人と直接話すこともできるので、ある種のステイタスとしてもプライドをくすぐり、需要が高まったのかもしれない。
一方、その即時性の高さゆえのデメリットもある。Twitterはテキスト、Instagramは画像で見せるSNSであるため、加工や虚像も作りやすいが、Clubhouseは音声のみのためアラが見えやすい。TwitterやInstagramであれば事務所のマネジメントが入る場合もあるが、即時性の高いClubhouseでは炎上しても事務所のフォローなどは不可能である。
また、「テレビと違って全然、話せない」「トークルームを仕切れない」といったことも明らかになり、良くも悪くも芸能人本人の実力がTwitterやInstagramよりも顕著に出てしまう。即時性の高さは、そのままMC能力や会話のキャッチボール能力、言語運用能力などがハッキリ表われるので、場合によっては自分の商品価値を下げてしまうことにもなる。そんな事態を恐れてか、ポジショントーク(自分の立場を考慮した話)ばかりとの批判もあるようだ。
「Twitter以上のバカ発見器」になる可能性も? 急速な下火とクローズドな場での発言が多くなっていくことの憂い
しかし、それでもClubhouseが芸能人・著名人に注目されたのは、一連の失言批判報道が背景にあったからかもしれない。つまり、森元東京五輪組織委員会会長の女性蔑視発言や、おぎやはぎの小木の娘への発言、松山ケンイチの「嫁」発言等々の“炎上案件”においては、Twitterはそれらの失言を批判・批評する場として機能し、出火・延焼の原因にもなっていた。そうしてメディアで発言しづらくなってきたところに、アーカイブが残らない音声のみのClubhouseが登場し、招待制という閉鎖性も相まって急速に普及したとは考えられないだろうか。
とはいえ、フタを開けて見れば、Clubhouseのクローズドなはずの発言もテキスト化され、ネットに流失していく。そして結果的には皮肉にも音声のみのClubhouse の登場によって、やはりLINEやDMなどのテキストベースのやりとりのほうがラクとする20代層をはじめ、自分で自由に編集や削除ができるTwitterのほうが使い勝手がよいとする声も増えている。
TwitterやInstagramよりもファンやフォロワー、異業種の人間たちと同じ空間を共有しやすいClubhouseではあるが、瞬発力が要求される場だけに、たった一言で一瞬にして信頼や人気を失う可能性もある。一方、キングコング・西野亮廣やオリエンタルラジオ・中田敦彦のように、オンラインサロン的な“囲い込み”ビジネスとしては最適なツールにも見える。今後、どのようにSNSとつき合っていくべきなのか、芸能人たちのSNS利用を通して、私たちはSNSとの向き合い方を学んでいくのかもしれない。